会員同士の日々のつぶやきや自己紹介、質問・お悩み相談などの一言メッセージです。
読みたい年度をクリックしてください。
質問や相談にお答えできる方は、ぜひ投稿をお願いします。
(閲覧は誰でも5件までできますが、投稿は「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」の会員のみ可能です。
会員のページより「皆さんの声」を投稿してください。)
 会員のみなさんの声※新しい順に表示しています。
会員のみなさんの声※新しい順に表示しています。

※新しい順に表示しています。
![]()
2025/06/18
さん (広島県)
広島市内各区に認知症の人と家族の会があります。南区では認知症の相談に特化して受けると言い張り身体介護の相談には対応しない運営をしています。参加の前日に電話させて、身体介護の相談には対応しないがそれでもよければ来ていいと伝えます。来たとしても対応しないので、その人は以後対応しません。そんな運営だから、参加者は極めて少数です、いないことも。この改善方を、認知症の人と家族の会県支部、南区地域支えあい課、市役所地域包括ケア推進課、人事課へ相談しても放ったらかしです。まあこちらの会も入会手続きが分かりにくく、350文字超えたら初めからやり直しです。
![]()
2025/05/21
吉 野 茂 樹(山口県) さん
令和2年より妻が、発病、投薬が始まり、現在5年目。料理・掃除と奮闘しておりますが、今、73歳我々の時代は仕事ばかりで、家事は全くの未経験者、電気釜のスイッチの入れ方が分からないところからのスタートで、すべてが見様見マネ。花嫁修業の勉強がしたい・・・。
![]()
2025/05/07
ばんばのばんちゃん さん
会の活動を拡げるためには、考えました。男性介護者と支援者の全国ネットワークの存在が、各市町村社協や居宅支援事業所などの、介護事業者に十分知られていません。そこで、各都道府県社協事務局あてに、一斉メール送信ないし、冊子類を送付するなどして、各都道府県社協から各市町村社協事務所等あてに、周知文章を送ってもらって欲しい。同様に、都道府県庁から市町村(基礎自治体)あて周知文章を送ってもらい、更には市町村から地域包括支援センター宛てに一斉メールで周知してほしい。
※非会員の方は最新の50件のみ表示されます。
会員の方はこちらよりログインしてご覧いただくと、全件表示されます。

※当ネットワークへハガキや手紙で届いたメッセージは、「ハガキより」として後日投稿しています。

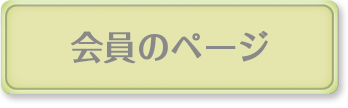
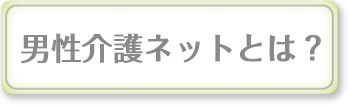
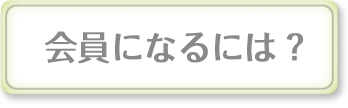
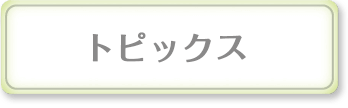
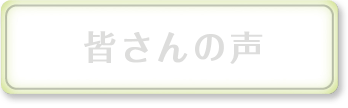
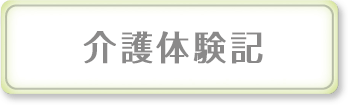
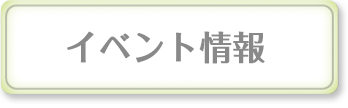
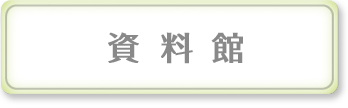
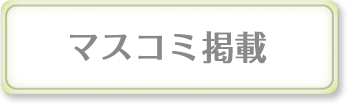
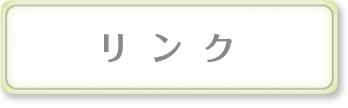
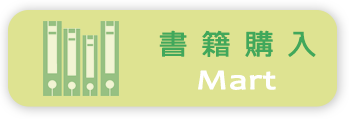
立命館大学人間科学研究所気付
Copyright(c)2009-2014 Danseikaigo All Rights Reserved.